歴史は繰り返す。技術もまた繰り返す。②
-Linuxを通してどんな技術にも強いエンジニアになる-
執筆者:岡田賢治
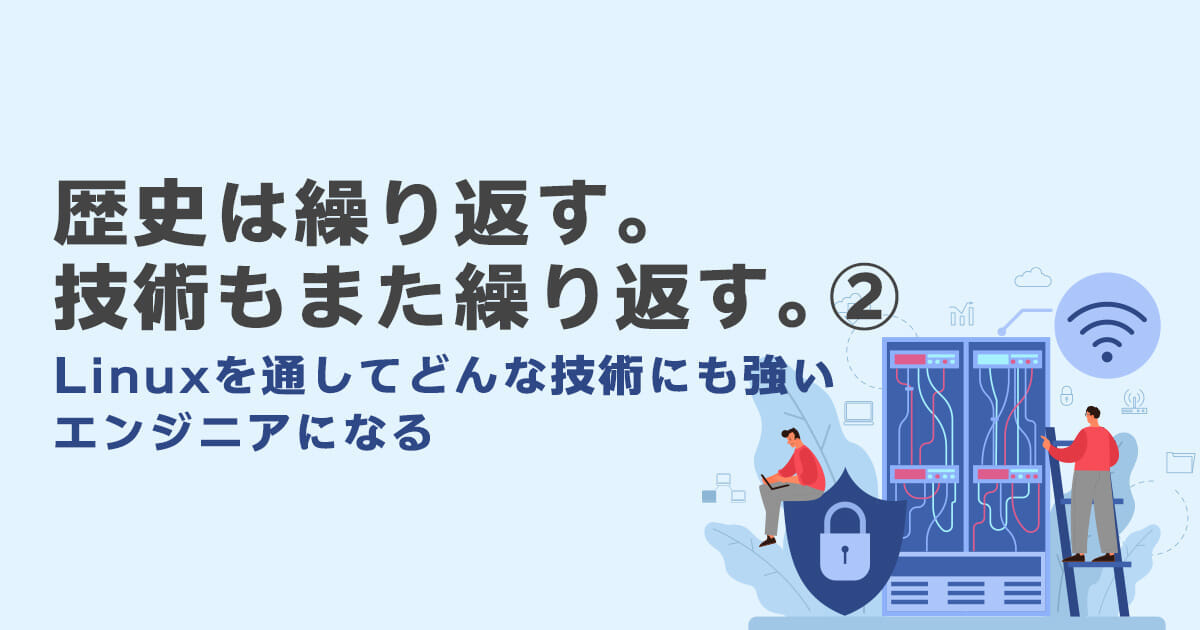
はじめまして。岡田と申します。普段、LPIの資格試験の普及をお手伝いしている者です。ここではIT技術全体的な観点から、Linuxの有用性を説明していきたいと思います。
前回の記事では、過去の技術トピックと現在話題の技術トピックを「繰り返す」という観点で説明しました。では、今回はそれらを学習する方法を考えてみましょう 。
最初に「踏破」できる人
このような技術トピックの学習を、最初に踏破できる人は誰でしょうか?
「踏破」と書きました。意味は「長く困難な道のりを歩き通すこと」です。イメージとしては、山道、あるいは山道すらもない悪路をなんとか歩いて前に進むような感じです。道・未開の分野の技術的トピックを身につけるとは、まさしくこのような感じです。前回の記事のように、技術トピックは「繰り返し」ます。従って、一度似たようなことを経験した人は、より簡単に理解が進みます。
よくプログラムを書く人が、「言語は1つをマスターしてしまえば、あとは応用が効く」という旨の発言をします。これも、「プログラミング言語の理解」という悪路を踏破したから、2回目の別のプログラミング言語の学習時に、前のトピックの理解を生かして学習がより早くできるわけです。
それでは、サーバーにおいてはどうでしょうか。サーバーではLinuxが圧倒的なシェアを誇っています。このLinuxの知識を身につけると、関連する技術の学習もスムーズに進みます。
UNIXとUNIX like OS
UNIXというOS
話が変わりまして、UNIXというOSがあります。現在UNIXと名乗れるOSは、当該団体に審査をしてもらい、認可を受けたOSのみが名乗ることができます。表記上は、登録商標の意味を込めて®️(Rを丸で囲っている。Registered Logoの意味)をつけます。身近なOSでは、Apple社のmacOSが2000年代真ん中ごろに、UNIXの審査を受けてUNIX®️と名乗れるようになっています。
UNIXの誕生や発展の経緯は、AT&Tのベル研究所とかSystem V・BSDの話などたくさんあり、ここでは割愛します。ただその流れで、UNIXのような挙動・構成をしながらUNIXではなくフルスクラッチで作成されたOSがあります。みなさんご存じのLinuxがそれです。
UNIXの正式な系統ではなく、またUNIXの審査も受けていないこのようなOSを、UNIX系OSとかUNIX like OSと呼んだりします。
UNIXの一派では、サーバ方面で現在一番使われているOSは、Linuxです。UNIXの一派で一番利用されているのがUNIX系OSというのもなかなか変わった話です。
Linuxのアプリケーションに相当する、パッケージにはさまざまなアプリケーションが提供されており、その中にはプログラミング環境も含まれています。プログラミング環境は、プログラムを作るのもさることながら、プログラムを実行する構成の理解も必要になります。さらにそのプログラムがTCP/IPで通信をすることになったら・・・理解の幅が無限に必要になります。
逆を返してしまえば、Linuxを学習しある程度のレベルになったということは、上記のことを全てマスターしているわけです。上記の内容を包括的に理解していることは、IT技術の理解につながります。とっつきづらい、がゆえに、一度理解してしまうと、本人のスキル向上につながります。
とっつきづらい、がゆえに・・・
Linuxを含め、UNIX/UNIX系OSの特徴は、そのとっつきづらさにあります。一般の利用者向けのOSでは、マウスがありGUIが用意され、となっています。もちろんLinuxにも、クライアント利用を目的とした環境はあります。しかし、Linuxが強みを発揮するサーバ向け環境は、「コマンド」の利用がメインです。
このコマンドが非常に多くあり、私も「よく使う・使わない」「勉強した・勉強してない・勉強した後に生まれた」まで含めると、全てのコマンドを網羅したとは、とても言えません。
無事コマンドをマスターしたとしましょう。今度は、Linuxの環境の話になります。Linuxは、UNIXも含めネットワークの機能であるTCP/IPを初期の頃から含めていました。このTCP/IPの繋がりが、今日のインターネットになっています。ですので、TCP/IPの挙動がわからずしてLinuxはマスターできません。
Linuxを学習したいが・・・
では、その素晴らしいLinuxを学習し始めたい・若手のエンジニアに学習させたい、と思った方もいると思います。Linuxの学習におすすめなのは、実機・実環境を備えて課題に沿って学習すること。逆に避けたほうが良いのは、教科書だけ読む頭でっかちの学習、あるいは、ろくに教科書を読まず現場経験だけ積む方法です。
ここで、私の過去の体験談を。
私がUNIXを勉強したのは、大学の学科ネットワークの管理でした。ただ、UNIX自体は現在のように豊富な書籍や資料、サーチエンジンやまとめサイトがあるわけではないので、師匠にあたる先生から、怒鳴られ怒られ「体で覚える」という学習姿勢でした。
これは、非常に強力です。「体で覚える」と絶対に忘れません。が、逆に弱点があります。「人を育てるのには最悪」ということです。
人材育成という観点では、この方式は最悪です。私のように趣味も兼ねてやる人間ならいいのですが、通常の方には時間が有限であり、それが社員教育となれば、短時間でスキルアップという効率性が求められます。効率性の側面から、「体で覚えさせる」わけにはいきません。
専門学校の授業という形で、私もLinuxを教えることになりました。「体で覚えた」身としては、「教えて教えきれるモノではない」というのが正直な感想です。ですが、教えなくてはいけない。
ちょうどその時にLPIC関係のお仕事をいただき、専門学校時の授業ノートと合わせて、教材資料を作り、以降LPIC関連の資格の普及をお手伝いしています。個人的には、「教えて教えられるモノではない」といった過去の自分に対する、「世間にLinuxとその学習に役立つLPICの資格試験を普及させる」という今の自分の挑戦でもあります。
LPICの書籍は非常に充実しており、現場で役に立つことを前提に試験範囲が構成されています。実際に試験を受けたり、書籍を監修していたりしますが、非常に項目は洗練されており、初心者のスキルアップに非常に役に立つ構成になっています。
Linuxの学習を進める方に、LPICに沿った学習をお勧めいたします。
執筆者
岡田 賢治
SESでエンジニア業務に従事する傍ら、LPIの資格試験の普及・コミュニティ活動にも関わる。
LPIでの講演実績、IT技術書の執筆多数。8年間の専門学校非常勤講師としての実績をもつ。
Linuxの知識やLPICの試験範囲を学ぶ

インターネット・アカデミーでは、Linuxの基礎から演習を交えながら知識を身につける研修をご用意しています。エンジニア部門に配属される新人のスキルアップはもちろん、非IT職の方向けのサーバー基礎研修、LPIC等の試験対策の研修も承っています。
貴社の受講者の知識レベルや学習の目的など、ご要望に合わせてカリキュラムのカスタマイズもできますので、Linuxの学習を検討している方はお気軽にお問い合わせください。
Linuxの人材育成について相談するデジタル人材育成・助成金のお役立ち資料をダウンロード

デジタル人材育成や助成金活用のお役立ち資料などをまとめてダウンロードしていただけます。コンサルタントへの無料相談をご希望の方はこちらからお問い合わせください。
- DX人材の育成&事例紹介 リスキリングのロードマップ付き
- デジタル人材育成に使える助成金制度
- デジタルスキル標準 役割別おすすめ講座

